
住宅ローンの記録
ボクは3年程前に新築の戸建てを購入しました。
既存建物付き土地を不動産屋の仲介で購入して解体してハウスメーカーで建てました。
その際に選択した金利は全期間固定金利(団信付き35年ローン)です。
金利は1.28%でした。当時の変動金利は0.65%位でしたので可能であれば変動金利がよかったですね。
固定金利を選択したのは単純にフラット35の審査が緩く(語弊がありますが・・・)通りやすかったからです。というのも、当時は転職して半年程で家を購入しようと無謀な考えをしていました。
変動金利の銀行で住宅ローンを組もうとしても1,500万円位(記憶があいまいですが)しか組む事が出来ませんでした。
フラット35(固定金利)だと倍の3,000万円位のローンを組む事が出来ました。
細かい理由は知りませんが審査が緩いって事なんですね。
固定金利と変動金利
ざっくりとした説明になりますが、固定金利は全期間固定と期間選択固定があります。
全期間固定金利はその名の通り、今後金利が上昇してもローン開始時の金利が変わることはありません。将来的に金利が上がる場合は得をしますが金利が下がる場合は損をします。
期間選択固定は、期間が決まっている固定金利です。例えば、10年固定金利でしたら10年間は金利を変えずに、ローンを組む事が出来ます。また、全期間固定に比べて金利が安く設定されているので、変動金利が激しく上昇しても10年で繰り上げ返済可能なら一番得ですね。(ボクにはできませんが)
変動金利は固定金利と比べて低い金利でローンを組む事が出来ますが、短期間で金利の見直しがされる。(期間は6ヶ月毎が多いようです)
ローン条件
ローン融資を受ける為にはローン審査を受ける必要があります。
審査を申し込むと審査機構を通して年齢・年収・勤続年数から貸出金額が算出されます。
携帯料金の延滞や借金の延滞が複数回ある等、審査に引っかかると融資を受ける事が出来ません。(俗に言うブラックですね)
引っかかる事は無いと思っていても、いくらの融資結果が出るかドキドキします。
借入可能額
融資額は審査によって決定するのですが、基本的に年収&現在受けている借金と合わせた返済比率によって決まります。
銀行などの金融機関・住宅金融支援機構などによっても異なりますが年収の6倍から10倍ほどで設定されます。私がローン審査をした時は転職したばかりだったので、満額で計算してもらう事が出来ずに苦労しました。一度ローン審査をすると半年程は前回の審査結果が残ってしまい、借入額を増やす事が難しくなります。
団体信用生命保険(団信)
住宅ローンを受ける際に検討する方が多いのが団体信用生命保険(団信)です。私も入りました。
団信はローンに付けておくと契約者が死亡や高度障害となり、その後のローン支払いが出来なくなった際に保険金で返済するというものです。団信に入る事でローン金利が高くなります。
私が団信に入ろうとした際は健康診断の血圧が引っかかり、再検査で何とか通してもらいました。
つなぎ融資
住宅ローンは自宅の引き渡しと共に融資を受ける事が出来るのですが、住宅を建てる際は土地の購入や着手金・中間金など、途中で支払わなければならない費用が色々あります。
「そんなお金ありませんが」って方の為に、少し高い金利で一時的に融資を受ける事ができます。それが【つなぎ融資】です。つなぎ融資は住宅ローンの融資を受けた際に返済しますのでその期間の金利が掛かります。
諸費用ローン
金融機関によって、住宅ローンに組み込む事が出来る項目と出来ない項目があります。例えば不動産取得税や登記費用等です。言い換えれば、住宅にかかる資金の全額を住宅ローン融資とする事が出来ない場合があります。購入時にはただの意地悪かと思いましたがルールなので仕方ないですね。
こちらも高めの金利で設定されており、別でローン設定されているので未だに支払っております。金利も高いのでこちらだけでも早めに繰り越し返済してしまいたいですね。
リバースモーゲージ
ボクには直接関係ありませんでしたが、家の購入をする際に流行っていた物です。
老後に生活資金に困ったり契約者の死亡後に自宅の処分を考えて設定する保険です。設定した期間内で自宅を担保に年金形式で融資を受ける方法です。満期になったり期間内に契約者が死亡すると担保物件を売却して債務を完済させます。もし、80歳とかで満期になって住むところが無くなってしまったら。と考えると恐ろしいですが、メリットを感じられる方は多いのかと思います。
まとめ
今回は、ボクの住宅購入を振り返りながら住宅ローンの解説をしました。
これから住宅購入を考えている方やボクと同じように住宅を購入し方に読んでもらいたいです。
今後は固定金利が更に上昇していく傾向かと思われます。
住宅の購入方法も新たな手法が取り入れられるのか目が離せません。新情報があれば記事にしたいと考えています。

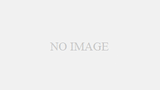
コメント